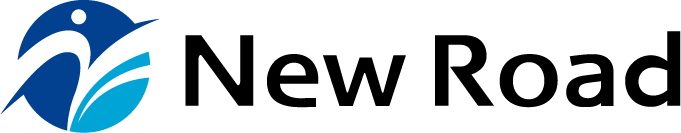卓越した技は見る人たちを夢中にさせる。しかし、人をもっと感動させるのは技ではなく、そこに込められた想いや覚悟ではないだろうか。旗やライフルを使い、音楽に合わせて視覚的表現を行なう集団演技・カラーガード。今回お話を伺った長野裕仁さんは現在、福岡県那珂川市で小中学生向けのカラーガード教室や中高生の指導などを行なっている。世界選手権優勝という実績を持つ長野さんだが、だからこそ大切だと考えていることがあるという。
目次
高校時代に初めて出会ったカラーガード

長野さんは、福岡県にある私立・大濠高校の出身。現在は共学だが、当時は男子校で運動部の多くが豊富な実績を有していた。高校入学後、思わぬ形でカラーガードに出会ったという。
「運動部に入ってもどうせベンチだと思い、高校からスタートできるものと考えました。そんなとき、吹奏楽部の先輩に肩を組まれて部室へさらわれ、『入部届を書いたら帰してやる』と。それでカッコいいのが良いだろうと、カラーガードに連れて行かれたんです。それが、カラーガードとの出会いでした。」
当時の長野さんは知らなかったが、大濠高校の吹奏楽部はマーチングバンドの実力が高く、全国大会への出場歴も豊富だった。強引な勧誘から始めたカラーガードだったが、同じように中学時代には運動部に所属していた初心者が多かったとのこと。音楽が好きでスポコンに似た感覚が肌に合った長野さんは、徐々に熱中していく。そして2009年、第37回マーチングバンド全国大会で金賞を受賞した。
ドラムコーインターナショナルに行くと決めたきっかけと、2年間で得た実績

高校卒業後は福岡大学に進学し、カラーガードも継続した。そんな中、大学1年生の夏に大きな転機が訪れる。高校生の頃からDVDで毎年追っかけていた、DCIことドラムコーインターナショナルという世界選手権。その中の1つのパフォーマンスに、目が奪われたのだ。
「ある団体が9.11のテロとその後を題材に、ニューヨーク市民や関わる人達を勇気づけるパフォーマンスをしていたんです。それにとても感動して、『これができるならアメリカに行きたい』と初めて思いました。」
行きたいという思いは、絶対に行くという決意に変わっていった。しかし、オーディションを受けるための渡航費や、滞在期間中の費用は実費である。さらに各地を転戦していくため、4月の終わりから8月末まではアメリカに滞在しなくてはいけない。大学生にとって越えなければならないハードルは多かったが、絶対に行くと決めた長野さんは両親を説得。アルバイトと両親からの援助でお金を貯め、もちろんオーディションに合格するための練習を欠かさず、その期間は休学することで1つずつクリアしていった。
そして2年生の冬。時間はかかったものの、感銘を受けた演目を生んだ振付師のいる団体のオーディションを受けて合格。初めての海外、加えて多国籍の集団に参加することになったが、果たして不安はなかったのだろうか。
「英語は全然できませんでした。でも、同じ団体に日本人が5人いて、2年目・3年目という方もいたので、最悪は聞けばわかるかなと。ですから、そんなに不安はなかったですね。」
ドラムコーインターナショナルは世界選手権であると同時に、青少年情操教育の側面も強い。そのため、参加者は21歳以下という年齢制限がある。また、全部で40以上のチームがあり、雰囲気も団体によって大きく異なっていたそうだ。
「小さい頃からずっとマーチングバンドやドラムを続けている子が参加する場所でもあれば、アメリカは夏休みが長いので、その間で非行に走らないようにという意味合いもあります。団体によっては禁止事項が多く、大人が完全統制して『君らはこうするんだ』という団体も。一方、自由に『君たちはもう大人なんだから自分たちでやりなさい』という団体もありました。」
1年目はBluecoats Drum and Bugle Corpsという団体に所属し、5位に入賞した。大会が終わると日本に帰国し、後期はお金を貯めつつできる限りの単位を取得。そして、2年目のシーズンにむけて再び渡米し、この年はBlue Devils Drum and Bugle Corpsという屈指の強豪に所属して優勝を果たした。このときの心境について、長野さんは次のように話してくれた。
「ものすごく嬉しかったです。でも逆をいうと、それだけでした。自分が登ってきた山の天辺はここだと見えていたから、驚きはなかったです。だって、2年目は優勝できる団体にいたから。優勝できると確信していたから、想像の上をいくことはなかったですね。」
大会の結果よりも大切なものとは

ドラムコーインターナショナルで優勝を果たした長野さん。このときの心境が、一つの考えに繋がっているという。それが、「大会の結果よりも大切なものがある」というものだ。その意味について伺うと、長野さんは次のように語ってくれた。
「当然、目指していたものだから嬉しいし、競争とか戦うとかいうことは好きです。でも、やり切ったときにそこで終わりなんですよね。別に何も残らないという感覚が僕にはありました。例えば、タイムを競うものには明確な基準があります。でもマーチングはもちろん、例えば音楽や舞踊・舞踏などアートやカルチャーに近いものは、誰がどんなに低く点数を付けたって良いものは良いんですよ。もちろん、大会に出るからには上を目指さなければいけません。でも、見ている人によって基準や価値観が変わるものに点数を付けることが、僕はあまりピンときていないんです。それよりアートとして残していくこと、カルチャーとして知ってもらうことの方が大事だなと。例えば同じフィギュアスケートでも点数を競うものと、プロスケーターのショーは別物じゃないですか。でも、それは別物で構わないと思っていて、僕が力を入れたいのは後者なんです。」
実際にそれを体現すべく、2015年に自分のカラーガードチーム『Flare Colorguard』を設立した。その中で、大切にしているのは「覚悟」だという。
「生のパフォーマンスを見に来るお客さんが見たいもの、感動するものって、ステージに立つ人の覚悟だと思うんです。その覚悟に合わせて、バックグラウンドが見ている人に伝わります。逆に言えば、パフォーマーはどんなに響かなくても、どんなに伝わらなくても届くようにと願い、とにかく球を投げ続けなければいけません。数年前の全国大会で僕のチームの演技を見て、泣いてくれている人がいて。大会の結果より、『届いたんだ』と思えたことが僕は嬉しかったですね。」
長野さんは現在、さまざまな会社に関わり多忙な日々を送る。その中の1つが、カラーガードのスクールだ。その活動が、子どもにとって表現の方法を自分で選ぶこと、どうすればできるようになるのか考えることの種になるのではという。
「昨年にカラーガードの小中学生向けの習い事を立ち上げ、先日開校したばかりです。もともと自分が立ち上げていたチームも、その事業体の中に組み込もうとしています。それぞれの形でカラーガードを続けたい人たちが、コストを払わなくて済むようにしたい。お金の問題で続けられない学生も多いですが、その理由はもったいないと思うんです。大前提として、カラーガードは表現の方法の1つでしかないと思っています。でも、強いて言えば旗を振る角度やスピードによって形を変えるし、表情を変わって見え方も変わる。そこは、他のものと少し違うかもしれないですね。カラーガードという表現の方法には、まだやれることがある。だから『なんとかできるよ』と思ったことを、人に対してもカラーガードに対してもどうにかしたくて、とにかくやっているだけなんだと思います。」
半ば強制のような形で、思わぬ理由から始めたカラーガード。しかしその後、人生の約半分もの年月にわたり、形を変えながら関わり続けてきた。これからも長野さんはカラーガードを通じて“本当に大切なもの”を伝えていくのだろう。
長野 裕仁(ながの ひろと)
福岡県出身。福岡大学卒。2009年 第37回マーチングバンド全国大会で金賞受賞。Drum Corps International World Championship 2013で5位入賞、翌年のDrum Corps International World Championship 2014では優勝した。現在は採用コンサルタントや公共事業に関わる仕事をしながら、中高生のカラーガード・マーチングの指導、モード株式会社で小中学生向けのカラーガード教室、株式会社アルモニでマーチングを中心とした楽器販売などを行なっている。

福岡県那珂川市在住のサッカー大好きフリーライター。地元・アビスパ福岡を中心に熱く応援している。趣味で書いていたものが仕事につながり独立。サッカー、スポーツ、インタビュー記事を中心に執筆中。